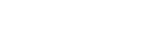今回は、前回の続きの作業として、「見本園」の整備、植樹を行いました。
見本園は、産業廃棄物不法投棄現場を唯一見渡すことができる展望台まで続く階段横にあり、かつて豊島に広がっていた自然植生を再現する場所となっており、豊島を訪れた方に対して、環境教育の場の提供をすることを目的として活動をしています。
前準備として見本園に土を運び入れる様子
今回植樹したのは、元々豊島に自生していた「アラカシ」、「トベラ」、「クスノキ」、「クロガネモチ」、「ネズミモチ」の5種類、合計30本植樹しました。
植樹の前準備の様子
植樹の様子
植樹した後に、豊島の植生が根付いている土地から種子の混ざった土を運び、植樹した見本園に撒く作業をおこないました。これにより、見本園が元の豊島の植生により近いかたちになります。
落ち葉を除去し土を集める様子
集めた土を植樹地に撒く様子

作業前

作業後
また、岡山大学が豊島の植生回復の研究をしている区画で、雑草を刈る作業を行いました。この場所は、2024年に見本園と同じように豊島の植生が根付いている土地から種子の混ざった土を運び、撒いた場所になります。種から芽が出て育ち始めていて、その芽の育成を促進させるために陽の光を妨げる雑草を刈りました。育ち始めている植物の芽も刈ってしまわないよう印をつけながら、手作業で行いました。
雑草を刈る様子

作業前

作業後
これらの活動はとても地道で、人手も時間もかかる作業です。このプロジェクトを通じて、自然を壊すのは簡単だが、元に戻すのにはとても長い時間がかかること、現在の植生を単に放置しているだけでは「元通りの自然」を回復することが出来ないことを学びました。そして、植生回復活動、見本園を通じて、豊島に訪れるか方への環境教育の場として活用してもらいたいという、瀬戸内オリーブ基金の想いに共感し、この活動を続けていきます。
今回は、産業廃棄物不法投棄現場を見渡すことができる展望台まで続く階段横に、豊島に自生している植物を植える「見本園」を作るための整備を行いました。雑草の除去、水や土砂の侵入を防ぐための土嚢の設置、竹の切り出し、竹で出来た柵の作成、イノシシ除けの柵の設置、苗木を植えるための砂の運搬などを行いました。
階段横の雑草を除去する様子

作業前

作業後

土嚢を作る様子

完成した土嚢
土嚢を見本園まで運び、設置する様子
竹を切り、運び出す様子
竹を割って柵を作る様子
柵を設置する様子
見本園に敷く土を袋に詰める様子
バケツリレー方式で砂を上へ運び、見本園に敷く様子

作業前

作業後
雑草を手作業で刈る様子

作業前

作業後

作業前

作業後
嶋教授は「本来の豊島の植生が分かるような見本園を、豊島でとれた竹や砂を使って作ることで、いずれ腐るもの、ゴミにならないもの、豊島の中にあるもので完結させたいと考えています。また、植生回復活動地の雑草は、養分が地上部にある夏場に刈ることで再び生えにくくしていきたいです。そのお手伝いをNGPさんにお願いしたい。」と語っており、植生回復活動地を広げるとともに、環境教育の場として見本園を活用してもらうことで、豊島にどんな植物があったのかを知ってもらえれば、との想いで活動を続けています。
今後も産学で連携し、引き続き取り組んでまいります。
今回は、産業廃棄物不法投棄現場を見渡すことができる展望台の整備を行いました。見学に来る方たちが転倒しないように足場の小石を取り除き、不法投棄現場の全体を見渡せるように周りの雑草を除去しました。作業前に比べ展望台の見晴らしは良くなり、階段の足場は安全に登れるようになりました。
展望台の雑草を除去する様子

作業前

作業後

作業前

作業後
展望台まで続く階段の足場を整備する様子

作業前

作業後
また、岡山大学が豊島の植生回復の研究をしている区画で枯れ松の伐採を行いました。放置すると幼虫が発生して植生を荒らしてしまい、本来の自然を取り戻すための多様な種の成長を妨げてしまいます。チェーンソーで伐倒して切り分けたあと、クローラーで外へ運び出しました。

枯れ松をチェーンソーで伐倒する嶋教授
伐倒した枯れ松を切り分けて、運び出す様子
嶋教授は、
「展望台を整備して環境教育の場にしたいと考えています。そのためには見学に来た方々が転ばないような足場の整備や、よく見渡すための雑草の除去が必要です。また、豊島の自然を取り戻すために、枯れ松を伐倒して幼虫の発生を防ぎ、より多くの種が成長することを目指していきます。そのお手伝いをNGP さんにお願いしたい。」と語っており、植生回復を進めるとともに環境教育の場を作っていければ、との想いで活動を続けています。
今後も産学で連携し、引き続き取り組んでいきます。
今回は、岡山大学が豊島の植生回復の研究をしている区画で、以前土を撒いた場所の雑草を刈る作業を行いました。
以前植栽した豊島に元々自生している植物は、撒いた土から小さい芽が生えてきているため、もう少し成長するように10cm上を刈りましたが、大事な芽も刈ってしまわないように手作業で刈りました。

嶋教授によるレクチャー

以前植栽した植物の芽が出ている様子
雑草を刈る作業
 作業前
作業前 作業後
作業後
また、不法投棄現場を見下ろせる展望台へ続く階段横の整備を行いました。階段横については今後も整備を続け、「見本園」として豊島に自生している植物を植えることを予定しています。
展望台に続く階段横の整備
 作業前
作業前 作業後
作業後
 作業前
作業前 作業後
作業後
嶋教授は、
「ここは不法投棄現場が見渡せる唯一の場所です。ここに見学に来る方たちが昔どうだったか、本来の豊島の植生がどうだったか看板や見本園を作って分かるようにしていきたい。その協力をNGPさんにお願いしたい。」と語っており、以前より本研究の成果が豊島の産業廃棄物不法投棄現場の植生回復の見本になれば、との想いで活動を続けています。
参加者からは、
「植生回復への道のりはまだまだ遠そうだが、みんなで協力して作業することにより、作業前はたくさん生えていた雑草がなくなってスッキリし、作業の成果が目に見えて実感できた。今後も継続して参加したい。」といった感想が聞かれました。
10月とはいえ暑い中での作業となりましたが、水分補給や日焼け対策をしっかり行ったうえで活動を行いました。
成長を阻害する植物や雑草の除去は定期的な作業が必要なため、今後も定期的に活動を行い植生回復に取り組んでいきます。
前回2024年2月、岡山大学が豊島の植生回復の研究をしている区画で豊島に元々自生している植物の種子を研究区画に撒き、成長過程を観察していく作業を共同で行いました。
今回の作業は、前回作業した場所の植生を促すためと、作業範囲を広げるために枯れた松の木を除去する作業と雑草を刈る作業を行いました。範囲を広げた場所には前回同様に「表土撒き出し法」を行い、1年目に種子を撒いた場所、2年目、3年目に種子を撒いた場所と、植生回復の経過が分かるようにしていく予定です。
研究区画の枯れた松を取り除き、重機で運ぶ様子
研究区画の雑草を地道に除去する様子
また、研究区画内に植えたコバノミツバツツジに「たい肥」を撒く作業も行いました。コバノミツバツツジは豊島に自生するツツジですが、非常に弱いため岡山大学で植生回復の一環として、コバノミツバツツジの種から苗木へと育成し、その苗木を一年間、地元の小・中学校に預けて毎日水やりをしてもらい、植樹する活動を行っています。
コバノミツバツツジの周りの雑草を除去して「たい肥」を与える様子
<産廃処分地展望台の整備>
産廃処分地の近くには現場を見下ろせる展望台があり、見学コースにもなっていることから多くの方が訪れます。今回の作業は、展望台からの視界を妨げている雑草の除去と、展望台に上るまでの階段横の整備を行いました。階段横については、今後も整備を続け豊島に自生している植物を植えることを予定しています。
展望台での雑草を除去する様子
展望台に続く階段横の雑草を整備する様子
嶋教授は、
「ここは、小学生をはじめ多くの見学者が通ります。階段の横には豊島に自生していた植物、コバノミツバツツジなども一緒に植えて、元々はこれだけの植物があったということを示したいと思っています。言葉で『豊かな自然がここにはあった』と言っても、今はどこにもないのですから。」と語っており、以前より本研究の成果が豊島の産業廃棄物不法投棄現場の植生回復の見本になれば、との想いで活動を続けています。
これらの活動は定期的な作業が必要であるため、引き続き取り組んでいきます。
今回は、岡山大学が豊島の植生回復の研究をしている区画で、豊島に元々自生している植物の種子を研究区画に撒き、成長過程を観察していく作業を共同で行いました。
種を撒くと言っても、売られている種を撒くのではなく、豊島の植生が根付いている土地から種子の混ざった土を運び、研究区画に撒く「表土撒き出し法」という手法で行われるため、初日は下準備として、研究区画の雑草を刈る班と、土を採取する場所の落ち葉や枝を取り除く作業をする班とに分かれて行われました。
研究区画の雑草を除去
土を採取する場所の落ち葉を除去
二日目は、山の斜面から土を研究区画に運び、撒くという作業を全員で行いました。表面から5センチくらいの土を集めて運ぶという作業で、体力を使う作業ではありましたが、元々岡山大学側の人の手が不足していた背景もあり今回の作業は産学共同だからこそ実現したと感じることが出来る作業となりました。
種子の集まりやすい斜面から土を採取
研究区画に土を運び入れ撒く
嶋教授は、
「山の斜面には、条件が良くなるまで発芽しない休眠している種子があります。それを研究区画に植えます。全部芽が出なくてもよいのです。その環境に合ったものだけ芽が出ればよいのです。」と語っており、以前より本研究の成果が豊島の産業廃棄物不法投棄現場の植生回復の見本になれば、との想いで活動を続けております。
枯れ松や雑草の除去は定期的な作業が必要なため、今後も定期的に活動を行い植生回復に取り組んでいきます。

NGPボランティアと、嶋教授(後列左から2番目)、学生さん、瀬戸内オリーブ基金の皆さん
今回は、岡山大学が豊島の植生回復研究をしている区画において、研究対象となる環境再生のために植栽した植物の成長を阻害する雑草の除去作業を行いました。豊島に元々自生している「ヌルデ」や「アカメガシワ」など実生の木もあるため、すべて手作業で行いました。今回の場所は毎年行っているツツジの植樹場所としても活用していく予定です。
 嶋教授から説明を受ける様子
嶋教授から説明を受ける様子 雑草の除去作業の様子
雑草の除去作業の様子 雑草の除去作業の様子
雑草の除去作業の様子 雑草の除去作業の様子
雑草の除去作業の様子
また、今年2月末に豊島小中学校によるツツジの植樹式(※1)が行われた場所において、ツツジの成長を阻害する雑草の除去を行いました。ツツジの周囲約1メートルを対象範囲として35か所、実生の木を見極めながら全て手作業で行いました。
嶋先生は「鳥が種を運んで来て、色々な植物が広がり、ここの条件に合った植物だけが残る。それが自然です。私たちができることは雑草を刈り、小さい実生が自力で大きくなる環境を作ってあげるだけです。ツツジだけは種が小さく成長が非常に遅いので、ここで種を取って私たちが2年育てて、豊島の子どもたちが1年育てて植樹をしています。高校に通うために島を出る子どもたちが豊島に帰ってきた時に、ツツジを植えた思い出が残せればいいなという想いで続けています。」と語られ、元の植生に戻す大変さと、「豊島の子どもたちにできること」のお手伝いをさせていただいたと実感することができました。
【ツツジの植栽地】雑草の除去の様子
 【ツツジの植栽地】雑草の除去の様子
【ツツジの植栽地】雑草の除去の様子 【ツツジの植栽地】作業前
【ツツジの植栽地】作業前 【ツツジの植栽地】作業後
【ツツジの植栽地】作業後
今回の作業は、昨年9月に行った活動の続きでもある、岡山大学が豊島の植生回復研究をしている区画のイノシシ対策を行いました。
研究区画の周りに設置しているイノシシ対策のネットが老朽化しており、そのまま放置するとイノシシに研究区域が荒らされる恐れがあったため、老朽化したネットを撤去して新たに金属製のワイヤーメッシュの柵を設置するとともに、研究対象となる環境再生のために植栽した植物の成長を阻害する枯れ松や、雑草の除去作業も行いました。
-

枯れ松の除去作業の様子
-

枯れ松の除去作業の様子
-

雑草の除去作業の様子
-

雑草の除去作業の様子
-

【ワイヤーメッシュ設置場所】
作業前
-

【ワイヤーメッシュ設置場所】
作業後
-

【枯れ松・雑草の除去作業】
作業中
-

【枯れ松・雑草の除去作業】
作業後
また、2月末に予定されている豊島小中学校によるツツジの植樹式の事前準備として、土を運び入れる作業を行いました。この土は、岡山大学が豊島の植生回復を行うために研究をしている区画の土で、学生の研究が一区切りついたことから、ツツジの植樹で再利用することになりました。土壌改良材や施肥された豊かな土であることから、豊島の子どもたちが植樹するツツジの根付きをよくすることが期待されます。
-

土留めの囲いの撤去の様子
-

土を運び出す様子
-

土を運び出す様子
-

土を運び出す様子
-

土の移動後に整地を行う様子
-

作業前
-

土留めの囲いの撤去後
-

整地後
今回は冬場で寒い中での作業となりましたが、防寒対策をしっかり行ったうえで活動を行いました。
枯れ松や雑草の除去は定期的な作業が必要なため、今後も定期的に活動を行い植生回復に取り組んでいきます。

NGPボランティアと瀬戸内オリーブ基金の皆さん
●岡山大学が調査・研究を行っている場所及び活動について
今回NGPが活動した場所は、産業廃棄物不法投棄現場すぐ近くの、豊島の産廃問題が起きる前の1960年後半に産廃事件を起こした首謀者が珪砂(ガラス原料)を目的とした大量の土砂の採取をした場所で、不法投棄現場同様に岩盤がむき出しの荒れ果てた土地でした。
2015年より、廃棄物対策豊島住民会議の安岐事務局長から豊島本来の植生回復について相談を受けたのをきっかけに、岡山大学の嶋教授は、この場所で調査・研究を開始し、定期的に雑草を刈りながら、元々生えていた約18種類ほどの植物を、種子から発芽したばかりの芽を育てる活動を3年ほど続けましたが、ウルシ、アカメガシワ、イヌザンショウなど、特定の植物しか育ちませんでした。
そこで、15~16種類の植物があった裏側の山林の攪乱されていない土地から、埋土種子を持ってきて30ヶ所ほど移植する作業を行いましたが、芽が出るところと出ないところがあり、調べてみると、岩盤までの深さが15cmを境に、浅いところは芽が出てもすぐに枯れてしまい、深いところは芽が育つということが判明しました。
そこから、大学の研究として、30cm、15cm、7.5cmの3パターンの土の厚さでどこが一番よく育つか調べて2年目になりますが、7.5cmではたくさん発芽しても全部枯れてしまい、30cm、15cmでは発芽する量は少ないものの、それが全部生き残って、大きくなることが分かりました。
今年は、できるだけ土を薄くしてより効率をよくするため、土地改良材や緑化資材などを試しながら検証しており、研究室の学生が卒業論文の研究として担当しています。
この場所は、種子から2年間育てたツツジを豊島の子どもたちが植樹する作業を、以前から行っていた場所でもあり、3年間ほど毎年ボランティアが草刈りをして種を蒔く活動を行っていました。コロナ禍もあり、ボランティアの人手が足らず、雑草や枯れ松はそのままに、イノシシ避けのネットが老朽化するなど、荒れた状態となってしまっていました。
せっかく子どもたちが植えた場所で、3年ほど活動していた場所でもあったので、そこを今回戻そうということで、今回のボランティア活動となりました。
●NGPの今回の活動について
この場所の環境再生を行うため、嶋教授指導のもと岡山大学が研究している区画の、雑草や枯れ松の除去作業と、老朽化していたイノシシ避けのネット撤去し新たにワイヤーメッシュを設置する作業を行いました。
今回新たに作業する場所では、老朽化したイノシシのネットに雑草が絡まり穴が空くなどしていたため撤去しました。最近では、イノシシが新芽を食べるなどの被害が多く出ており、イノシシ除けの強化を行うため、金属製のワイヤーメッシュの柵を設置しました。
また、ワイヤーメッシュを設置した区画内も、枯れ松や雑草が多く生い茂り、研究対象となる環境再生のため植栽した植物の成長を阻害していたため、除去を行いました。
-

枯れ松の除去作業の様子
-

枯れ松の除去作業の様子
-

雑草の除去作業の様子
-

雑草の除去作業の様子

ワイヤーネットの撤去の様子

ワイヤーメッシュ設置作業の様子
-

【ワイヤーメッシュ設置場所】
作業前
-

【ワイヤーメッシュ設置場所】
作業後
-

【枯れ松・雑草】除去前
-

【枯れ松・雑草】除去後
また、今年5月に作業した見学道の階段脇の植栽地も夏場ということもあり、また雑草が生い茂ってしまっていたため、再度除去を行いました。
-

【見学道の植栽地】の雑草除去
-

【見学道の植栽地】の雑草除去
-

【見学道の植栽地】作業前
-

【見学道の植栽地】作業後
また、今年2月に豊島小・中学校、岡山大学、瀬戸内オリーブ基金と合同で植樹※1した、コバノミツバツツジの植栽地では、成長を阻害する雑草の除去を行いました。
-

【コバノミツバツツジの植栽地】
雑草の除去作業の様子
-

【コバノミツバツツジの植栽地】
雑草の除去作業の様子
-

【コバノミツバツツジの植栽地】
作業前
-

【コバノミツバツツジの植栽地】
作業後
嶋教授は、
「不法投棄現場が40年間ほったらかしになったらどうなるかというと、今回の作業場所のようにしかなりません。それではだめだろうということで研究がスタートしました。
現場はツツジの花が咲き始めているし、様々な植物も出てきて、大きくなっています。
放置すると松枯れと雑草がひどい状況となりますが、土を盛って手入れを続ければ順調に育つという見本になればよいと思っています。」 と語っています。
今回は残暑厳しく、35度を超える中での作業となりました。定期的な水分補給をしながら熱中症対策を行い、額に汗し活動を行いました。
枯れ松や雑草の除去は定期的な作業が必要なため、今後も定期的に活動を行い植生回復に取り組んでいきます。

嶋教授(後列右から2人目)と学生たち(前列右から2人目・3人目)、NGPボランティア
岡山大学大学院環境生命科学研究科の嶋一徹教授は、2015年1月に廃棄物対策豊島住民会議の安岐正三事務局長から「何となく植物が生えて緑になっているが、元の自然とは違うのではないか」との相談を受けたのをきっかけに、不法投棄現場周辺の植生を調査しました。
調査の結果、かつてはコバノミツバツツジやナツハゼなど約18種類ほどの植物が生えていましたが、不法投棄によって植生が破壊され、半分以下に減ってしまったことが判明。安岐事務局長より、不法投棄現場に元の豊かな自然が戻るまで産廃問題が終わらないこと、自然の力を使って植生が回復する手法を示してほしいことなどの強い想いを受け、2015年4月より、調査研究と植生回復活動に取り組んできました。

岡山大学大学院環境生命科学研究科
嶋一徹教授
今回、NGPが豊島の環境再生を目指し、掲げたゴールを達成するため、今後の活動について瀬戸内オリーブ基金に相談。岡山大学の行っている植生回復活動の話を受け、目指す姿、想いが同じであるということ、活動を進めていく上で岡山大学側の人の手が全く足りていない状況を聞き、豊島の植生回復の手助けができるならばと産学連携による活動をこの度スタートいたしました。
岡山大学では、植生回復の一環として、コバノミツバツツジの種から苗木へと育成しその苗木を一年間、地元の小・中学校に預けて毎日水やりをしてもらい、不法投棄現場に植樹する活動を行っており、NGPは2021年2月、豊島小・中学校、岡山大学、瀬戸内オリーブ基金と共同で植樹式に参加するなど、以前から交流がありました。
今回NGPが岡山大学と連携して作業を行った場所は、不法投棄現場の見学に利用するために瀬戸内オリーブ基金が設置した見学道の階段の脇です。ここは、岡山大学の主な植生回復活動の現場であり、この場所で活動を行うことにより、不法投棄現場の見学だけではなく、環境教育を行うことを目的とした場所です。
見学道の植栽地は、不法投棄の影響で植生が崩壊し地面が露出した状態であったため、斜面の崩落を防ぐ目的で植えられた外来種のコマツナギが繁殖。不法投棄が行われる前の植生とは異なる状態になっており、僅か数種類の植物しか生育しておらず多様性が極めて乏しいのが現状です。 「見た目は緑が回復しても豊かさは回復できていません」と嶋教授は語ります。
そこで、見学道の植栽地では、本来自生していた多様な植物を、島内で採取した種子から育苗して植栽しています。
見学道の植栽地で植栽している植物
- シャリンバイ
- イヌザンショウ
- クスノキ
- イヌビワ
- アカメガシワ
- トベラ
- ヒサカキ
- コバノミツバツツジ
- タラノキ

【見学道の植栽地】植栽された植物のネームプレート
NGPとしては、今回初めてこの活動に参加し、嶋教授と土壌環境管理学研究室の学生たちによるレクチャーを受けながら、植生された植物の成長を阻害する雑草・外来植物の除去、しがら柵の補修、樹木への名札付け、雑草繁茂抑制と土壌乾燥を防ぐための堆肥の敷設を行いました。

作業の説明をする嶋教授

嶋教授(後列右から3人目)と学生たち(前列3人)、NGPボランティア

作業前

作業後
また、今年2月に豊島小・中学校、岡山大学、瀬戸内オリーブ基金と合同で植樹した、コバノミツバツツジの植栽地では、成長を阻害する雑草の除去と植栽地の脇の水路の側壁崩壊を防ぐための土嚢の設置を行いました。
【コバノミツバツツジの植栽地】雑草の除去作業の様子

作業前

作業後
【コバノミツバツツジの植栽地】土嚢の設置作業の様子
参加者からは、
「一度破壊された自然は長い時間をかけないと元に戻せないと改めて感じた」
「豊島の環境が完全に元に戻るまで活動に関わりたい」
といった声が聞かれました。
夏場にかけて雑草が繁茂していくため、今後も定期的に活動を行い植生回復に取り組んでいきます。
豊島小中学校、岡山大学土壌環境管理学研究室、瀬戸内オリーブ基金と共同でツツジの植樹式を実施しました。
かつての豊島には、多くのツツジが自生していましたが、不法投棄によってその多くが失われました。
岡山大学は、オリーブ基金の「豊島・ゆたかなふるさとプロジェクト(国立公園原状回復事業)」のなかで、不法投棄現場の植生の回復活動を行っており、ツツジの育苗・植栽活動もその一環として、2017年より毎年行われているもので、今回で5回目となります。
NGPも、岡山大学と同様に「豊島・ゆたかなふるさとプロジェクト」に参加していることから、今回初めてツツジの植樹式に参加となりました。
植樹式では、岡山大学の学生と嶋一徹教授のレクチャーを受けながら、豊島小中学校の児童・生徒とNGPの本部職員が一緒に「コバノミツバツツジ」の苗木約40本の植樹と水やりを行いました。
NGPにとっても、豊島の子どもたちと交流しながら植生回復に貢献する意義深い機会となりました。
参加した子どもたちからは、「ツツジが大きく育って欲しい」「元の豊島に戻って欲しい」といった声が聞かれました。
「柚の浜」の、笹や木の根、雑草の除去を行いました。元々荒れ果てていた場所は今後整地され、オリーブの木が植えられる予定です。 また、瀬戸内オリーブ基金の呼びかけにより、愛媛大学で教員をされていた方と、岡山大学農学部の学生2名も参加。 学生たちは大学で豊島の植生回復の研究を行っており「豊島の環境再生の役に立てるならば」と今回参加することになりました。
















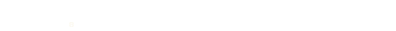



















































 作業前
作業前 作業後
作業後




 作業前
作業前 作業後
作業後 作業前
作業前 作業後
作業後




































 作業前
作業前 雑草の除去
雑草の除去 土の運び入
土の運び入 作業完了
作業完了
 嶋教授から説明を受ける様子
嶋教授から説明を受ける様子 雑草の除去作業の様子
雑草の除去作業の様子 雑草の除去作業の様子
雑草の除去作業の様子 雑草の除去作業の様子
雑草の除去作業の様子


 【ツツジの植栽地】雑草の除去の様子
【ツツジの植栽地】雑草の除去の様子 【ツツジの植栽地】作業前
【ツツジの植栽地】作業前 【ツツジの植栽地】作業後
【ツツジの植栽地】作業後